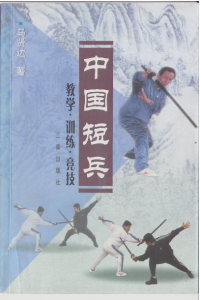
こちらでは馬賢達先生の著作である中国短兵の一部を私が和訳したものを紹介しております。
大変に貴重な内容が込められたものであり,日本における中国武術研究の一助となれば幸いに思います。
なお,訳には至らない部分もあるため原文を付しておきましたので興味のある方はそちらをご参照ください。
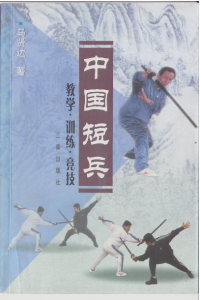
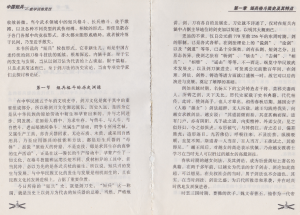
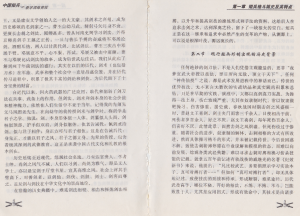
短兵格闘の歴史的淵源
中華民族5000年の文明史において、剣刀文化は重要な部分をなしている。剣刀文化は悠久の歴史を持ち、中華民族の原始労働のなかで芽生え、進歩し、発展してきた。原始における人の集団は生きるために、獣と戦い、人と戦い、自然と戦い、部族間の闘争までもしてきた。生産活動とはいえども道具を用いて争ったし、また、生産工具とはいえども武器の要素を含んでいた。無論、石や木、あるいは自然を器具として用い、その器具を応用する技能や方法は皆、後の兵器を生み出す母体となった。「原始人の狩りは競技ではなく生きるための生産活動だ」といわれるけれども、この果てしなく長い生産活動がすべての文化を育んだのであり、格闘技能とともに長さも材質も違う道具を運用するということは、真っ先に各種の兵器の萌芽を思わせられるのである。だからこそ、短兵器の発生と発展、中華民族文化の発生と発展とは機を一にしていると言え、かつ民族文化の発展過程上重要な位置を占めていると言えるのである。今日いうところの短兵史とはつまり剣刀史である。短兵とはいわゆる歴史上の剣刀を代表とするような短兵器の総称である。もちろん厳格に述べるのであれば剣と刀には各自の発展史があるが、刀については詳しくは述べない。短兵の中で主要な地位を占める剣史に加えて簡単に述べ、もってあらましを明らかにするのみである。はるかな昔、紀元前770年~紀元前220年における東周の時代、剣の形成は定まり、すでに深奥な剣法理論が存在した。中華民族の武術発展史をざっと見るに、剣刀の進歩史は紀元前の数百年間の間に剣法理論や鋳造法など多方面において一時の隆盛を極めたであろう。ゆえにそれは後の進歩と発展において重厚な基礎を築いたといえる。例えば呉越の時代、天下の宝剣の鋳造者である干将・莫邪夫妻の鋳する剣は天下無比であったと歴代の史家が史書典籍に載せて代々伝えている。この時代は、剣法の巧手をも輩出していた。春秋の後期、越国の女子(「越女」と称する)の剣法は群を抜き、誰も敵わなかった。越王勾践は呉を討伐するため、越女に剣法を教えてくれるよう求めた。越女は言う、「その道は易くその意は深し、道に門あり、また陰陽あり。おおよそ手を使う戦いというものは、内は精神が充実し、外は柔和で穏やかである。見るは愛想のよい婦人のようであり、奪うは獰猛な虎のようである。(以下略)」。越王はこれを聞き越女に敬意を示し、越女に命じて当時誰も敵わなかった越女の超高等剣技を将軍や兵士に教えさせた。春秋時代の越女の剣法と剣術理論は、後世の剣壇において著名な典籍となった。二千数年前、越女を女子剣撃の代表として、剣術理論は超絶に高まっていたようである。思うに、夫権社会の当時において男子剣法すらも遜色を失っていたであろう。実際、当時の剣技、剣論の凄さは後代においても推賞と承認をうけ、流行し定着し進歩発展していった。
三国時代、魏文帝曹丕は一代の帝王にして建安文学の創始人の一人であり、その剣術の高さは歴史上の名剣家の一人に数えられている。曹丕は幼き頃より武術を学び騎射弓矢は終身衰えず、さらに剣法は多くの師についており、かつては河南の史阿から学び同時に名剣手の王越の正伝を得ている。ある日、相撲の名手である将軍郭展と剣について論じあった。酒が入って熱くなり、二人は芋を剣の代わりにして腕比べをした。曹丕は郭の腕を三度打ったが郭は納得せず、もう一度やろうということになった。郭展は今度は額を打たれた。曹丕と郭展の剣法試合の故事は後世の武壇の良い話となった。我々はこのことから二千年前も剣法が盛んであったことを知ることができる。以後の時代においても剣術及び刀術は軍事、武術、社会の中でずっと盛んな位置を占めており、歴代の伝習過程において蓄積された剣技と剣論は後代にまで残る貴重な財産である。
近代になって火器が広汎に使用されるようになり、剣刀は軍事的な重要性は低くなっている。しかし、剣法と剣術、そして剣そのものの社会的価値と精神性は当時に劣るものではない。私の師である馬鳳図先生について記憶していることがある。幼年時の私に剣術と剣学を伝授するときに、剣学は君子の学だと言っておられた。馬鳳図先生は言う、「剣の形は人体に似ている。剣纂は人の頭に似て剣柄は人の頸に似る、剣鍔は人の両肩に似て剣身は人の躯体に似る。剣を持つあるいは佩くということは君子とともにあるようなものだ。君子のように身を正すべし」。まずは身を正し、君子の雰囲気を才とし、君子の徳で身を立てる。先代達が伝授したものは深遠な武徳教育を含んでいたのだ。これぞまさに中国古代文化と礼教の根本であると言える。
歴史の流れを近現代までくだり社会の名流を総観するに、官吏貴人から学者紳士に至るまで、やはり剣の気風は衰えず、人々は剣を習い剣は優雅さを醸していた。すなわち文人学士もまた、庁堂書斎に宝剣を懸けて高貴さのシンボルとしていたのである。剣と剣技は中国文化において崇高な地位を占めていると言える。
浩瀚の歴史典籍の中に剣術で比武をするような描写を探すのは難しく、剣術の資料とすることはできない。このことは後の人が剣術を追求し深奥へ至ることに対して大きな空白を残した。短兵はまさに継承と追求の中で必然的に生まれた変革の産物であり、根源よりゆるぎなく遥かな流れの中にあるものだと言える。
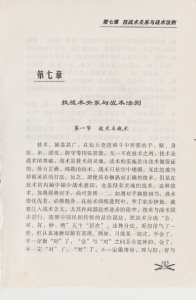
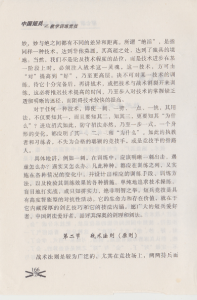
技術と戦術
技術とは深い教養である。短兵格闘において必要とされる手、眼、身法、歩、進攻、防守などの招法(実戦技)は、技術の列に加わらないものは一つもない。技術は戦術の基礎であり、戦術は技術の魂である。戦術の実施は技術を行う上での保証であり、正確で熟達した技術が無ければ戦術はただの空中楼閣にすぎず、巧妙で魂の入った打法を組むことはできない。反対に、正確で熟達した技術を備えていても、技術の中に戦術の意識が欠けていれば、それは魂のない技術である。このような技術でも相手が弱ければそれなりに威力を発揮するが、相手が互角、もしくは戦術変化に優れたものであるならば、必ず勝利の方法を探さねばならない。技術訓練の過程においては、手を挙げ歩を起こすという始まりから戦術の含意が注入されているのだ。とりわけ一部の技術の進歩の過程において技術と戦術は同時に進んでいく。中国民間の伝統的な品位の説法に照らし合わせてみると、技術とは「会、好、対、妙、絶」の五つのレベルに分けられる。このような分け方は、ちょっと俗気があるように見えるが、まじめに技術を磨くにはとても道理があるものだ。例えば、ある一つの技を修練することは“学会了”(学んで出来るようになった)ではあるが、必ずしも“学対了”(学んで正しく出来るようになった)とは限らない。“会”と“対”の間には差異がある。“対”は必ずしも“做得好”(上手く出来ている)とは限らない。“対”と“好”、“好”と“妙”、“妙”と“絶”の間には皆、不同の差異が存在する。いわゆる“絶活”とは、同様の技術ではあっても「絶対なる一」の境地に達したもののことを言うのである。もちろん、我々は技術程度の品位を論じているのではなく、技術進歩の階段を上るときには必ず、この魂ともいえる戦術を注入しろと言っているのである。これにより技術は“対”から“好”の段階へと高まり、さらに高次のレベルにも到達できるのである。決して、ある一つの技術訓練が完全に成し遂げられてから再び戦術を講じたり、技術と戦術を分けて訓練するなどということをしてはいけない。これは間違いなく技術が上達するまでの時間を遅らせ、技術への理解を妨げるからである。どのような技術であろうと、すなわち刺す、劈く、点く、挑むなど、その用法についての其の一を知るだけでなく、其の二、其の三、更に其の“なぜ?”までも知る必要がある。進攻の招法についてはこのようなものであり、防守の招法についてもまた然りである。一歩一式(技の形)ばかりか、体勢の変化に至るまで、みな其の一、其の二、其の三および“なぜ?”を明らかにしなければならない。このような取り組み方をする指導者や習練者が、優れた競技者、あるいは優れた指導者になれるのである。
具体的に述べよう、例えば「刺す」という技において、訓練においては「刺す」で相手を攻撃して、実に会えばどうするか?虚に会えばどうするか?をはっきりさせなければならない。おおよそこの種のことは皆、訓練の系列に存在しなければならず、更には各種の状況の変化の中で実施されなければならない。並びに相応の訓練手段、訓練方法を設計し、訓練の効果を検証しなければならない。単順に技術操法を追求し、盲目的に打ち合いを行い、あるいはムキになって実力を知ろうとすることは、決して賢明な判断とは言えない。短兵競技とは高度知能型の対抗性運動を具現化したものなのだ。その生命力と存在価値は、内蔵される深遠な剣芸技巧と理念にこそあるのだ。ゆえに多数の短兵愛好者、中国剣法愛好者たちよ、その深奥な剣理と剣法をしっかりと見定めよ。